

「地元民しか読めない」と思う大分県の市町村名は?【人気投票実施中】
九州の東岸にあり、北は福岡県、西は熊本県、南は宮崎県に接している「大分県」。温泉の源泉数・湧出量ともに全国1位を誇る「おんせん県」として知られています。中でも「別府温泉」や「湯布院温泉」などは全国的にも有名ですよね。
そんな大分県には、パッと見ただけでは読み方に悩んでしまう珍しい地名が少なくありません。そこで今回は「大分県で『地元民しか読めない』と思う市町村名は?」というテーマでアンケートを実施します。まずは編集部がピックアップした三つの市について見ていきましょう。
臼杵市

大分県東南部に位置する「臼杵(うすき)市」。「臼杵」という地名は、臼杵市稲田の臼塚古墳にある「石で作られた武人の像」に由来していると考えられています。この武人の像が臼(うす)と杵(きね)に似ていて、地元の人に「うすきね様」と親しまれてきたのが「臼杵」の地名の起こりだとする説もあるようです。
臼杵といえば、国宝・臼杵磨崖仏(うすきまがいぶつ)が有名です。臼杵磨崖仏は岩壁に直接彫り込まれた仏像で、平安時代後期から室町時代初期のものだと考えられています。ただ、「誰が何のために彫ったのか」はわかっていません。
杵築市

大分県の北東部にある「杵築(きつき)市」は、東に伊予灘、南に別府湾を望む風光明媚(めいび)な街です。城下町として知られ、市の中心部には杵築城跡や武家屋敷、石壁・石畳の坂道など江戸時代の面影を感じられる風景が残っています。
杵築周辺は、古くは「木付」と書き記されていました。初めて「杵築」の表記が登場したのは1712年のことで、6代将軍徳川家宣公の朱印状に「豊後国杵築領」と記されています。このとき、なぜ「木付」ではなく「杵築」とされたのかは今のところ明らかになっていません。
国東市

大分県北部の国東半島にある「国東(くにさき)市」。豊後風土記には、ヤマトタケルの父・景行天皇が熊襲(くまそ)の征伐のために周防灘を渡った際に、国東を見て「あれは国の埼(さき)か」と言ったと記されています。これが「国東」という地名の由来になったともいわれています。
国東半島は、日本古来の神道と仏教とが融合した「神仏習合」発祥の地。六郷満山(ろくごうまんざん)と呼ばれる独特な山岳宗教文化が根付いています。また、国東半島に広がる岩峰には、鬼たちが住む異界「大魔所」があると考えられていました。現在も、鬼にまつわる伝説や史跡、伝統行事が数多く残っています。
「地元民しか読めない」と思う大分県の市町村名は?
ここまで、大分県の三つの市を紹介してきました。あなたが「これは地元民しか読めない!」と思う大分県の市町村名はどれですか? 選択肢は大分県にある18の市町村です。その市町村を選んだ理由やおすすめスポットなども、コメント欄にぜひお寄せくださいね。
- 投票期間にかかわらず終了することがあります。
- 設問および投票結果は予告なく削除することがあります。
- 不正投票対策のため一部プロバイダ(海外等)からの投票ができない場合があります。
- プロキシサーバーを使用している場合投票できないことがあります。
参考
- 歴史(臼杵市)
- 杵築市 | 18市町村について(おおいた暮らしの第一歩)
- 広報きつき 平成24年6月号(杵築市)
- 「くにさき学」まるわかりガイドブック~知って・調べて・伝えよう~(国東市)
- こんなまち くにさき(国東市)
- 鬼が仏になった里「くにさき」(日本遺産ポータルサイト)
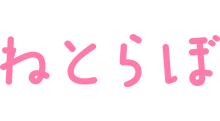





















 FEEDBACK
FEEDBACK